しょうゆについて
しょうゆの種類
醤油を大きく分ければ5種類
古くから日本各地で生産されてきたしょうゆは、それぞれの地域の嗜好や醸造の歴史などにより、さまざまな個性を持っています。その種類は、日本農林規格(JAS)によって、こいくち・うすくち・たまり・さいしこみ・しろしょうゆの5つに分類されています。

濃口醤油 -こいくちしょうゆ-
こいくちしょうゆは、全国のしょうゆ出荷量の約84%を占める最も一般的なしょうゆです。塩味のほかに、深いうま味、まろやかな甘味、さわやかな酸味、味をひきしめる苦味を合わせ持っています。調理用・卓上用どちらにも幅広く使える、まさに万能調味料です。

淡口醤油 -うすくちしょうゆ-
「淡口」と書いてうすくちと読みます。関西で生まれた色の淡いしょうゆで、しょうゆ出荷量の約13%を占めています。発酵と熟成をゆるやかにさせる食塩を、こいくちより約1割多く使用。素材の持ち味を生かすために、色や香りを抑えたしょうゆです。素材の色を美しく仕上げる炊き合わせ、ふくめ煮などの調理に使われます。

溜醤油 -たまりしょうゆ-
たまりしょうゆは、主に中部地方で造られる色の濃いしょうゆです。トロ味と、濃厚なうま味、独特な香りが特徴。古くから「さしみたまり」と呼ばれるように、寿司、刺身などの卓上用に適するほか、加熱するときれいな赤みが出るため、照り焼きなどの調理用や、佃煮、せんべいなどの加工用にも使われます。

再仕込醤油 -さいしこみしょうゆ-
さいしこみしょうゆは、山口県柳井地方で生まれ、山陰から北九州地方にかけて多く造られてきました。他のしょうゆは麹を食塩水で仕込むのに対し、生揚げしょうゆで仕込むため「再仕込み」と呼ばれています。色・味・香りとも濃厚で、別名「甘露しょうゆ」ともいわれ、刺身、寿司、冷奴など、主に卓上でのつけ・かけ用に使われています。

白醤油 -しろしょうゆ-
しろしょうゆは、愛知県碧南市で生まれた、うすくちしょうゆよりさらに淡く琥珀色のしょうゆです。味は淡白ながら甘味が強く、独特の香りがあります。色の薄さと香りを生かした吸い物や、茶碗蒸しなどの料理のほか、せんべい、漬物などにも使用されています。
しょうゆの製法
本醸造方式
しょうゆの伝統的な製造方法です。蒸した大豆(脱脂加工大豆)と炒った小麦をほぼ等量混合し、種麹を加えて「麹(こうじ)」を造ります。これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味(もろみ)」を造り、攪拌を重ねながら約6~8ヶ月ねかせます。麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて分解・発酵が進み、さらに熟成されてしょうゆ特有の色・味・香りが生まれます。

しょうゆの特性・規格
官能検査でしょうゆの特性である色・味・香りなどを厳しくチェックし、合格するすることが必要です。検査は(財)日本醤油技術センターが実施する「醤油官能検査員認定試験」に合格した者が行います。しょうゆは5種類それぞれに、色・味・香りの総合的な特性をもっています。個々の特性をわかりやすく表わすために、しょうゆの生産量の約8割を占めるこいくちしょうゆと比較してみます。
表-1 しょうゆの特性
| 特性 | こいくち | うすくち | たまり | さいしこみ | しろ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色度(番) | 透明感のある明るい赤橙色(色度10~13が一般的です) | こいくちより淡い(こいくちと比較して約1/3の淡さです) | こいくちよりかなり黒味がかっている(こいくちと比較して数倍こくなっている) | たまりと同程度(こいくちと比較して数倍こくなっている) | 美しい琥珀色。5種類の中で最も淡い(こいくちと比較して約1/5の淡さです) | ||
| 味 (%) |
味の基本的な成分 | 窒素分 | 1.5~1.6 | 1.15~1.2 | 1.6~3.0 | 1.6~2.5 | 0.4~0.6 |
| エキス分 | 16~19 | 14~16 | 16~27 | 21~31 | 16~24 | ||
| 食塩分 | 16~17 | 18~19 | 16~17 | 12~14 | 17~18 | ||
| 香り (HEMF:ppm) |
しょうゆの基本となる香り HEMF(甘いカラメル様の香り) 200 |
うすくち、さいしこみ、たまり、しろの順にHEMFの香りは少しずつ弱くなってきます。 | |||||
味の基本的な成分である窒素分、エキス分、食塩分数値は特級実績値(財)日本醤油技術センター資料
※色度の番数は「しょうゆ標準色」の番数です。(表-2しょうゆの種類と等級・成分等参照)
しょうゆの等級の種類
JASの認定工場でつくられ、JAS規格に合格したしょうゆはJASマークをつけることができますが、非認定工場の製品にはJASマークはつけられません。したがって、しょうゆにはJASマークのついているものとついていないものとがあります。ただし、認定工場の製品にはJASマークをつけるか、つけないかは任意とされています。
JASマークのついているものには「特級」「上級」「標準」のいずれかの表示がしてあります。(下段のJAS品質標準マーク)「特級」の表示は本醸造方式のしょうゆと、特例として「さいしこみしょうゆ」の混合醸造方式に限って認められています。しょうゆのうま味成分であるグルタミン酸やその他多くのアミノ酸類は、必ず窒素分を含んでいるのが特徴です。したがって、しょうゆ中の窒素分の多いものほど、うま味のあるしょうゆということがいえます。また、色の度合いや無塩可溶性固形分(エキス分)、直接還元糖などの分析値及び官能検査についても品質標準に合格していなければなりません。5種類のしょうゆの等級(品質基準)と窒素規格値(成分量)等は表-2.に詳しく載っています。
JASの品質標準マーク
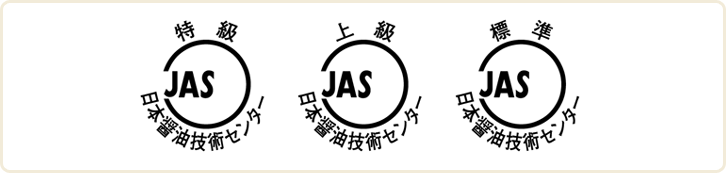
成分は全窒素分、無塩可溶性固形分、直接還元糖の分析を行い、規格値の範囲に、また、色度については「しょうゆの標準色」に照らしてその範囲内に入っていることが必要です。
表-2 しょうゆの種類と等級・成分等(規格値と実績値( )内)
| 種類 | 等級/成分等 | 全窒素分(%) | 色度(番) | 無塩可溶性固形分(%) | 直接還元糖(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| こいくち | 特級 | 1.50以上 (1.50~1.60) |
18未満 (10~13) |
16以上 (16~19) |
‐ |
| 上級 | 1.35以上 | 〃 | 14以上 | ‐ | |
| 標準 | 1.20以上 | 〃 | ‐ | ‐ | |
| うすくち | 特級 | 1.15以上 (1.15~1.20) |
22以上 (30~32) |
14以上 (14~16) |
‐ |
| 上級 | 1.05以上 | 〃 | 12以上 | ‐ | |
| 標準 | 0.95以上 | 18以上 | ‐ | ‐ | |
| たまり | 特級 | 1.60以上 (1.60~3.00) |
18未満 (1~2) |
16以上 (16~27) |
‐ |
| 上級 | 1.40以上 | 〃 | 13以上 | ‐ | |
| 標準 | 1.20以上 | 〃 | ‐ | ‐ | |
| さいしこみ | 特級 | 1.65以上 (1.65~2.50) |
18未満 (1~2) |
21以上 (21~31) |
‐ |
| 上級 | 1.50以上 | 〃 | 18以上 | ‐ | |
| 標準 | 1.40以上 | 〃 | ‐ | ‐ | |
| しろ | 特級 | 0.4以上 0.80未満 (0.40~0.60) |
46以上 (51~53) |
16以上 (16~24) |
12以上 (12~21) |
| 上級 | 0.40以上 0.90未満 |
〃 | 13以上 | 9以上 | |
| 標準 | 〃 | 〃 | 10以上 | 6以上 |
しょうゆのJAS規格及び( )内実績値は(財)日本醤油技術センター資料
※成分の表わし方:しょうゆの成分量は通常100mlあたりに含まれる成分の量(g)で表します。たとえば、全窒素分1.50%というのは、1.5g/100mlを表します。
※色度の番数は「しょうゆの標準色」の番数です。番数が小さくなるほど色がこくなり、番数がおおきくなるほど色は淡くなります。
特選と超特選の違い
しょうゆは、JAS規格により、「特級」「上級」「標準」に分けられています。そのうち特級だけに「特選」「超特選」という表示を使うことができます。
特選という表示はこいくち、たまり、さいしこみしょうゆでは、うま味成分である窒素分、うすくち、しろしょうゆでは無塩可溶性固形分(エキス分)がそれぞれの特級に比較して10%以上多いものに表示することができます。 超特選の表示については、さらに多く20%以上多いものとなっています。
表-3 特選・超特選の表示規準
| 用語 | 等級 | 種類 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 特選 | 特級 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.1倍以上 |
| うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.1倍以上 糖の添加不可 |
||
| 超特選 | 特級 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.2倍以上 |
| うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.2倍以上 糖の添加不可 |
※5種類のしょうゆの特級の窒素分、エキス分は表2を参照。